下水処理場のしくみ
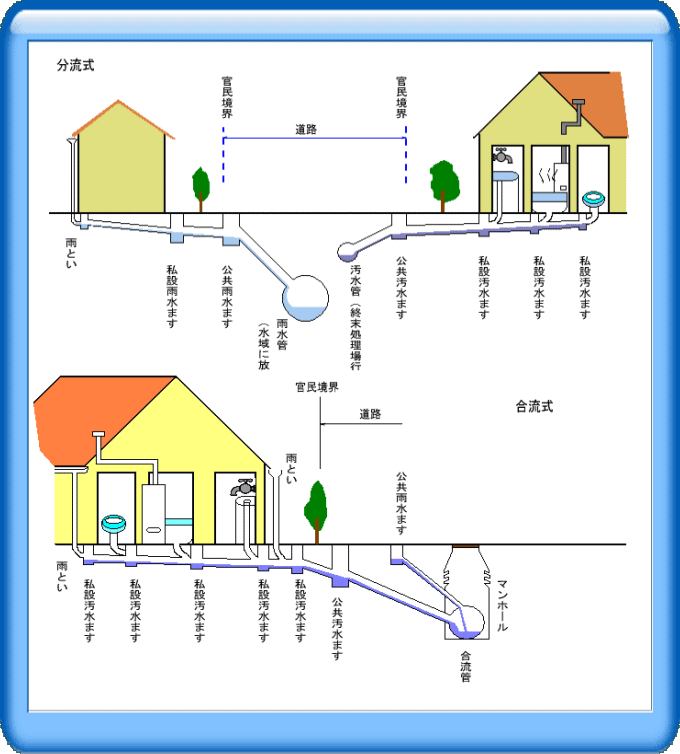
排水設備と公共下水道
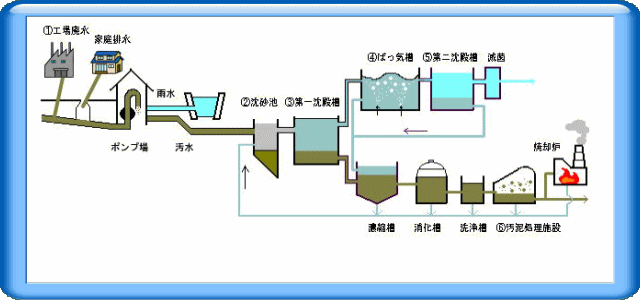
|
①工場廃水・・・工場は除外施設を設置した上で排水しなければならない。 |
|
②沈砂池・・・処理場に流れ着いた下水はここでゴミ・砂等を沈殿させて取り除きます。 |
|
③第一沈殿槽・・・沈砂池で除去し切れなかった細かい汚れを取り除きます。 |
|
④ばっ気槽・・・活性泥(微生物が含まれているドロ)を下水に加え、微生物が活動しや |
|
⑤第二沈殿槽・・・汚れが沈みやすくなった下水をゆっくりと流し汚れを沈めます。上澄み |
|
⑥汚泥処理施設・・・沈殿槽で沈んだ汚泥を脱水・焼却等の処理をします。 |
|
下水道には汚水と雨水を同じ管で流す合流式下水道と別の管で流す分流式下水道とが |
| 下水道の役割としては主に次のようなものがあります。 |
| ①水洗便所の普及を始めとし、汚水を速やかに適切に排除することにより衛生環境の向上と 快適な生活環境を提供する。 |
| ②汚水を浄化して放流することにより、自然環境に対する悪影響を軽減する。 |
| ③雨水を適切に排除することにより、浸水対策を行う。 |
| その他にも、最近では |
| ・下水処理によって生じる汚泥や水資源としての処理水の有効利用。 |
| ・汚泥の焼却熱の有効利用。 |
| ・処理場の敷地の有効利用。 |
| ・放流水の落差を利用した発電。 |
| ・下水配管の有効利用(電力ケーブルや通信ケーブルの敷設スペース) |
| などが新しい下水道の有効利用方法として考えられています。 |
| ①依頼する工事店を決める | 指定業者に見積りを依頼してください。(各市より配布される 指定業者の一覧表等を参考にしてください) 見積りや説明を参考にして工事を依頼する業者を選択して ください。 |
| ②改造資金の支払計画の検討 | 工事費用の支払計画を立ててください。費用が準備できない 場合は融資斡旋制度をご利用ください。(詳しくは市の下水道 管理課か指定業者までお尋ねください。) |
| ③工事の申請を行う | お住いの市の下水道管理課へ工事の申請をします。融資の 申し込みもこの時行ってください。(通常、指定工事業者が代行 いたしますのでご依頼ください。) |
| ④接続工事を行う | 市より工事の認可が下りた時点で工事を行うことができます。 平均的な工事期間は1~3日間ほどですが、その間水を流せ ない期間があります。工事業者からよく説明を受けてください。 |
| ⑤市の検査 | 工事終了後、市に工事完了届・下水道使用開始届を提出します。 (指定業者が行います。)提出後、市が検査を行います。 |
| ⑥下水道の使用開始 | 市の完了検査に合格すると検査済証が交付され、下水道の 使用開始となります。 |
※排水設備工事は、市の指定工事業者でなければできません。各市の下水道管理課に
お尋ねください。
※※工事完了後、下水道使用開始届を市に提出された時点から下水道使用料金が付加されます。
見積りを依頼する click!
下水道に接続することにより次のようなメリットがあります。
| ①コンクリート製ためますから、樹脂製のインバートますへ変更 コンクリート製のますは耐水性に弱く水分が浸透しやすく、また割れや底抜けを起こしやすく 漏水による住宅への悪影響を与える恐れがありましたが、耐水性に優れ密閉度の高い樹脂 製ますを使用することによりこれを解消しました。 溜め水をしないことにより、悪臭や害虫の発生が抑えられます。 |
| ②宅内からの流出口にはトラップますを設置 トラップを付けることにより、宅内への悪臭や害虫の侵入を防止します。 |
| ③浄化槽は解体して撤去もしくは埋設 浄化槽を使用しなくなるので、汲み取り費等の維持費用がかからなくなります。また、悪臭や 害虫の発生が無くなります。 |
| ④管径は100mmを使用 原則的に管径100mmのパイプを使用して埋設して敷設します。つまりや滞水を起こしにくく なります。 |
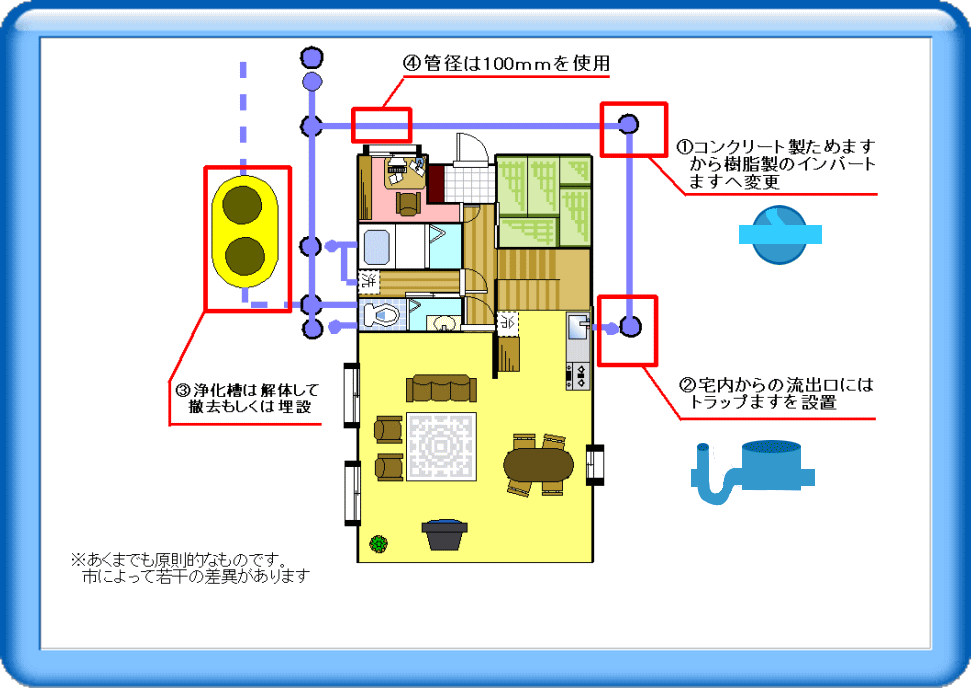
下水道の再利用は次のようなものが考えられてます。
| ①処理後に発生する処理水や汚泥等の再利用。 |
| 1.処理水を水資源として活用する。(親水施設への利用、工業用水への活用、処理水 の水温・水量の安定性を活用した発電、ヒートポンプによる地域冷暖房等。) |
| 2.汚泥の再利用。 農地、緑地への還元。(但し、環境への配慮から基準を満たさないものに関しては 利用不可。) 溶融化して建築資材等に利用する。 |
| ②処理に伴う熱等の利用 |
| 1.汚泥の焼却熱と処理水を利用した自家発電。 |
| 2.焼却熱を利用した空調、温水施設。 |
| ③施設の有効利用 |
| 1.処理池の敷地の有効利用。(地下に処理施設、その上に公園等の公共施設) |
| 2.下水道の暗渠を利用して、通信ケーブルや電力ケーブルを敷設する。 |
| Q.下水道への接続は何時までに行うのですか? A.浄化槽を使用しているご家庭では、供用開始がなされたら、遅滞なく速やかに、 汲み取り便所を使用しているご家庭では3年以内に下水道へ接続することが 義務付けられています。尚、浄化槽使用の場合は市によって期間が明示されて いることがあります。詳しくは市の下水道管理課でお確かめ下さい。 |
| Q.下水道への接続工事とはどのような工事ですか? A.家庭の台所、風呂場、トイレ、洗面所などから流出する汚水や工場、事業所等 から発生する廃水を一括して、設置した公共ますを経由して取付管より下水道 本管へ流入させるための工事です。 大まかに分けると、下水道に対応した排水管路の設置、浄化槽の廃止工事 汲取り便所の場合は水洗便所への改造工事)、公共ますの設置及び取付管 への接続工事となります。 |
| Q.下水道への接続は必ずしなければいけないのですか? A.必ず接続工事をしていただかなくてはなりません。合併浄化槽を除き、現在使用 されている単独浄化槽や汲取り式のご家庭で排出されたトイレ以外の汚水は 未処理のままで流域に放流されています。現状の水質汚染の最大の原因は無自 覚にのまま排出される生活廃水であるといわれています。 合併浄化槽におきましても、残念ながら使用者の処理性能や管理に対する関心 の低さや法的基準の曖昧さ等の問題から浄化設備として十分に機能しているとは いえない状態です。 これらのことを合わせまして、早急に水質汚染の問題に対処していくには速やか に下水道に接続していただきたいと思います。 |
| Q.下水道に切り替えることによって下水道料金の負担はどの程度になりますか? A.下水道料金は上水道の使用量を元に算出され、二ヶ月に一度水道料金とともに 請求されます。使用する量によって加算される割合も変わりますが、平均して上 水道料金の約70~80%が加算されます。 但し、浄化槽の維持費(点検・ブロアーポンプの電気代等)や汲取り費が相殺 されるので全体の負担額としてはそれほど大幅な変化はありません。 |
| Q.下水道にはどんなものでも流せるのですか? A.下水道はどのような汚水でも処理できるわけではありません。規定で定められた 以上の悪質汚水が流入すると下水管が損傷したり、処理場の機能が働かなくなる 恐れがあります。このような汚水を排出する事業所・店舗等は除外施設の設置と 届出が義務付けられており、基準内の水質まで処理した後、下水本管に排出する こととなります。 また、一般のご家庭においても台所で発生する生ゴミや油、トイレで使用するトイ レット・ペーパー以外のもの(非水溶性のもの)を流すのは排水管をつまらせたり汚 物の腐敗を招くので流さないで下さい。同様の理由でディスポーザーは使用しない で下さい。 |
| Q.排水管のメンテナンスはどのようにしたらよいですか? A.定期的に汚水ますのふたを開けて点検・清掃をしてください。ひんぱんに行う必要は ありませんが半年に一度くらいの割合で行うとよいでしょう。定期的に行うことにより 排水管の寿命を長くすることとなり漏水やつまりも未然に防げます。 台所の油や溶け残った洗剤等は凝固してつまりの原因となりますので注意して下 さい。また、汚水ますや排水管の近くに樹木がある場合は樹根による破損や変形を 起こす場合があるので注意が必要です。 専門的な点検や清掃を施工業者や専門業者に依頼することもできます。 |
| Q.使用しなくなった浄化槽はどうするのですか? A.空のまま放置することは土圧にによる損壊等強度的な面で出来ないので、取り壊して 土砂で埋めてしまうか撤去することとなります。水を張って放置しておくことは害虫の 発生や水の腐敗等衛生的な面でお奨めしません。 また、市町村によっては補助金制度を設けて雨水再利用施設として活用することを 推奨しています。詳しくは各市町村の下水道管理課までお問い合わせください。 ※浄化槽の型式によっては利用出来ないものもあります。 |
下水道工事に関するよくある質問を次にまとめました。この他の疑問がありましたら、
こちらまでお気軽にお問い合わせください。
| 下水道は現時点ではいくつかの解決していかなくてはならない問題点もあります。 その主なものを次に挙げます。 |
| 1.未整備地区への早急な敷設。 現在の水質汚染の状況は一刻も早い対策が必要となっており、早急な下水道の 整備が望まれます。しかし下水道を作るには莫大な費用と時間がかかり一朝一夕 にできるものではありません。闇雲に大規模な下水道計画を立てるよりも地域の 事情や自然環境・都市計画に応じた下水道を考えることが必要です。 そのためには公共下水道だけではなく、合併浄化槽のような個人下水道との併用 も考慮していこうという動きもあります。それには行政による品質基準と維持管理 基準の明確化と適切な指導と使用者の汚水排出に対する関心の向上が必要です。 |
| 2.下水道の整備や維持管理に伴う費用の軽減と財源の確保 前項でも述べたように下水道事業はそのものが後発事業でもあるため莫大な費用 を必要とします。この財源は各自治体の予算だけではなく国庫からの補助を受けて いるのが大半の下水道事業の現状です。 下水道の維持管理費には下水道使用料を充てるとしても、それまでの支払利息や 新設の下水道の工事費による財政の逼迫と必要性の板ばさみで非常に苦しい状態 にあるというのが下水道事業の実情です。 これらを解決してしていくには ・効率的な下水道計画の立案 各地域の実情や将来の都市計画に見合った計画だけでなく、財政的な回収率も 考慮に入れて経済状況の変化にも対応出来るような計画を立てることが必要です。 また計画の情報や工事の発注なども適正になされているかなどの実務的な情報も オープンにして地域住民の方に積極的に関心を持ってもらうことも必要でしょう。 ・他事業との併用で包括的に財源を確保する。 下水道事業を単独事業と考えず、下水道施設の併用(排水管を通信ケーブルの 通路に用いる。汚水処理施設に公園等の公共施設を併設するなど)や下水道が 整備されることによって利益を被る他事業(流域治水事業など)の予算を流用でき るようなフレキシブルな体制作りが必要とされるでしょう。 ・下水道が整備されたら出来るだけ速やかに下水道に接続する。 せっかく下水道が作られても利用されなければ宝の持ち腐れです。また下水道 使用料が回収できなければ下水道施設の維持管理もままなりません。速やかに 下水道に接続するようにしてください。 などの方法が考えられます。 |
| 3.汚水処理技術の向上 残念ながら現在の汚水処理場の能力は万能ではありません。特に古い処理場で は過去の水質基準に沿って作られているため除去できない物質もあります。こういっ た施設の改善とともに水質基準も見直していかなければなりません。 また効率的な汚水処理のための技術開発や経験を積んだ技術者の育成なども必 要な課題です。 なにより必要とされるのは家庭からの排水から出来るだけゴミを取り除く、合成洗 剤等を極力使用しない、汚水排出量を減らすために節水をするといった地域住民の 方のご理解と協力だと思われます。 |
| 以上いくつかの点を挙げましたが、この他にも地域によって種々問題がありますが、 重要なことは行政任せの下水道計画ではなく、地域住民が積極的に関心を持ち参加 していくことと、各個人が自分の排出する汚水の管理に責任を持つことでしょう。 |